通訳案内士の試験を受けることに決めたけれど、気が付いたら試験日までもうあと残りわずか・・・ということはありませんか?
本当は1年掛けてじっくり勉強したかったけれど、何とか残り2か月で集中して勉強したいという方に、学校には通わず自己流で通訳案内士の試験に合格した私が、残り2か月になった時点で行った勉強方法を紹介します。
最後の2カ月どのくらい集中して勉強するかで必ず結果は変わってきますので、頑張って実行してみてくださいね!
通訳案内士試験に関するまとめ一覧はこちら
↓
通訳案内士試験まで残り2カ月間の綿密な計画を立てる
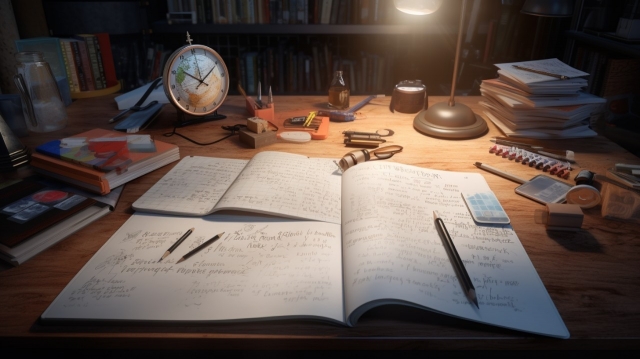
これから日本史の試験勉強に取りかかる方は、2カ月という短い間で、まずどこからスタートしたらよいいか迷ってしまいますよね。
そんな時はまずは綿密な計画表を作り、勉強の進め方を決めてしまいましょう。
なぜなら、やみくもに問題集を解いたり、参考書の一番はじめから読み始めたり、一部の時代のことだけ集中して勉強しても試験には受からないからです。また、本当にこの勉強法で良いのかと何をしているか分からなくなり、勉強が続かなくなってしまいます。
あらかじめ、細かいスケジュールを決めてしまうことで、その計画表に沿って、きちんと勉強を進めていくことが出来ます。
自分の勉強方法に合った計画表を作ってみよう
では、具体的にどのようにスケジュールを作ればよいのでしょうか?
私が作った下の表を参考にしてみてください。

まずは本日から試験日までの日を書きます。その下に枠をいくつか作っておきます。(実際に書き込んだ内容は次の項目で紹介します)
スケジュール表が出来あがったら、いよいよ勉強内容を振り分けします。ただ、適当に振り分けてしまっては意味がありません。短い期間しかないので、いかに効率よく勉強出来るか考えましょう。
試験勉強を効率よく行うためには
- どんな試験問題が出るのか理解する
- 歴史の大枠から詳細へと順に理解していく
ことが大切です。
通訳案内士の日本史の試験でどんな試験問題が出るのかを理解する
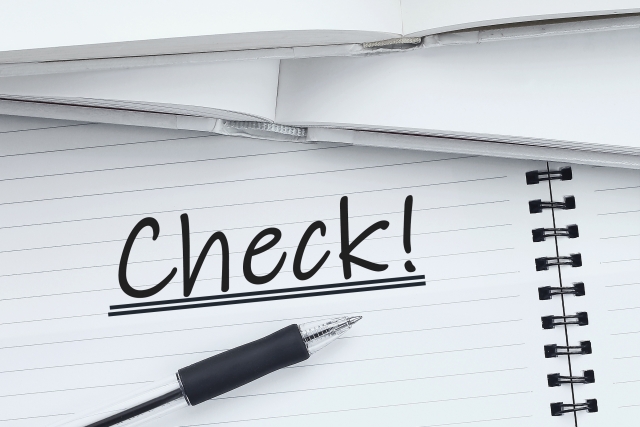
スポーツだってなんだって誰かと対戦する時は相手のことをよく調べますよね。
試験も同じです。どんな試験問題が出される傾向にあるのかは、しっかり理解してから試験勉強に取り組みましょう。
同じ日本史の試験でも、学生の頃に受けた日本史の試験と通訳ガイド試験では、問題の出され方も問われる事も違います。
もう一度、この試験はガイドになるための試験、ということを思い出してください。
「どういうこと?」と思った方はとりあえず、2018年と2019年の過去問を解いてみましょう。
※著作権の関係上、写真は塗りつぶされています。
どうでしょうか。初めて通訳ガイドの試験問題を見た方は驚かれたかと思います。「問題がかなりマニアックで一般的ではない!!」、と思われたのではないでしょうか。
そうなのです。中学や高校で受けた日本史の試験とは違い、問題も選択肢も長く、細かいことを聞かれます。
通訳案内士の日本史の問題は3つのタイプに分かれる
「とてもこんな試験に受かる気はしない」、と早々に諦めそうになりますが, 対策をしっかり取ればチャンスはあります!
まず、問題をよく分析して3つのタイプに分けて、それぞれのタイプの問題でとるべき点数について考えてみましょう。
日本史の問題は次の3つのタイプに分けることができます。
- 勉強したところで、よっぽどのマニアでないととても正解出来ない問題
- きちんと勉強すれば確実に正解出来る問題
- 落ち着いて考えれば正解出来る問題
それぞれのタイプについて、細かくみていきましょう。
マニアックな問題に対する対策

試験の始めからマニアックな質問が出ても驚いて慌ててはいけません。いきなりですが、マニアックな質問に対する対策は・・・捨ててしまいましょう。
考えても分からないような問題に時間を掛ける必要はありません。
通訳案内士試験の日本史の問題数は40問で40分で解きます。また、合格点は70点です。要は30点落としてもギリギリ合格出来るのです。
試験中に大切なことは、どの問題に時間を掛け、どの問題を瞬殺でいらないと判断するかということです。大体10問くらいがこのマニアックな難問に当たると思います。
ちなみに、通訳案内士の日本史の試験はマークシートです。4択ですから、単純に考えれば、すべて同じ解答番号を選べば25点取れるわけです。捨てる問題は全部②にするとか予め決めておくと良いかもしれません。
問題を出す方からしたら①をなんとなく正解にしたくない傾向があるのでしょうか。例えば、2019年度の解答は① 4 ② 14 ③ 10 ④ 12でした。
試験問題をサラッと見て、これはマニアックな問題だなと判断したら時間をかけずすぐ次の問題にいくようにしましょう。
きちんと勉強すれば確実に正解出来る問題は絶対に外さない
マニアックな問題を捨てる分、絶対に失敗してはいけないのが、確実に点を取れる問題を外さないということです。
この割合を高くすればするほど合格は近付きます。基礎的なことをしっかりと勉強していれば、試験中は時間を掛けることなく、一瞬で答えられる問題です。
基本的な問題がどんな問題かいうと、例えば、2019年の問題には次の問いがあります。
8代将軍徳川吉宗が実行したBの政治改革を示す語句として適切なものはどれか
→Bが何か、選択肢を見るまでもなく、『享保の改革』だと 答えられるようにしましょう。
勉強するべきことは次の項目で書きたいと思います。絶対に落とさないで答えたい問題は大体、40問中15問くらい(40点くらい)が目標です。
特に注意した点として、このタイプの問題は勘違いやマークシートのぬり間違いがないように、見直しを忘れないようにしましょう。
落ち着いて考えれば正解出来る問題
最後の問題のタイプは、「落ち着いて考えれば正解できる問題」です。このタイプの問題が一番重要で、ここでの正答率が合否を分けることになります。マニアック問題が20点分あるとしたら、残り10点以上間違えてしまうとアウトです。
もしかすると、たった1問間違えたことにより不合格になってしまうかもしれません。そのためにはじっくり時間を使ってよく考えて解答する必要があります。
このタイプの問題には、難しい文章で紛らわしいけれど、良く考えたら簡単な問題もあります。
例えば、次の2019年の問題を解いてみましょう。
A 1644、わが国を代表する俳人□が伊賀国上野で生まれる。
B 藤堂高虎が伊賀上野城を拡張(大幅改修)する
C「本能寺の変」に遭遇した徳川家康は、伊賀の間道を抜けることにより~
D 織田信長がそれまで在地土豪の連合支配が行われていて伊賀を武力で制圧する
問:古い順番に正しく述べたものは。 ①A-B-C-D ② A-B-D-C ③ B-A-C-D ④D-C-B-A
→この問題、Bがいつかなんて分かんないよ!と思うのですが、Bは全く無視して解ける問題です。 この問題で重要なのはただ1つ!Cの年号がいつかということ。
本能寺の変が1582(イチゴパンツと覚えましょう)年とさえ知っていれば、 CはDより後(本能寺の変で織田信長が死んだのはさすがに常識としておきます)、 AはD&Cより後ということが分かり(答え書いてあるし・・・) D→C→Aが成り立ちます。これに合うのは④のみですね。
このように、長文問題は一見難しそうですが、よく考えてみたら 解ける問題もあるので、こういう問題を落とさないようにしましょう。
他にも、一見難しいのが正しい文を選ぶ長文問題ですが、日本史の基礎をしっかり 勉強していれば残り3つの選択肢の間違いのキーワードが見えてくる問題が多いです。長文にくれぐれもまどわされないように!!

日本史の勉強するべき順番を理解しよう
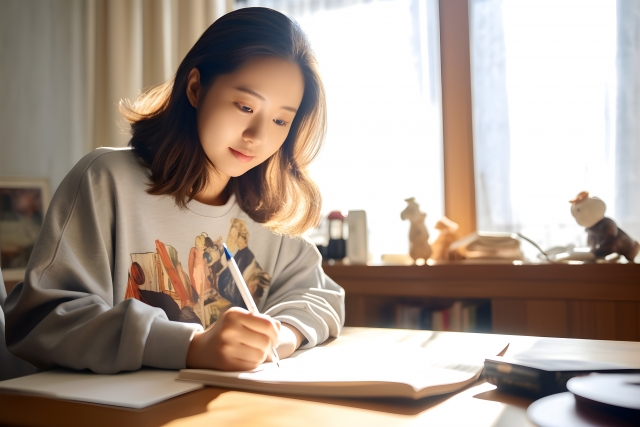
問題を実際解いてみて、通訳案内士試験の問題は長文が多く、 単純に答えられない問題やマニアックな問題が多いということが 分かりましたね。
しかし、同時に基礎的な日本史の勉強は、やはり重要だということも分かったと思います。
マニアックな問題を解くカギは普段から色々な媒体を見たり経験する、ということですが、残り2カ月しかない時点では基礎力をアップする勉強が必要です。
日本史を理解するには大きな枠から理解して序々に小さな事柄へと勉強を移していく、と私は考えています。
歴史は決して単独でひとつの事柄が成り立っているわけではありません。その時代がどんな時代であったかを理解せずひとつひとつバラバラに覚えても、頭に残りません。
それは、まるで、大きな森の中の小さな枝ひとつを見ているよう。全体像を把握して、必要な部分ごとに勉強していくことで、それぞれのパーツで、何を勉強するべきなのかが見えてくるのです。
日本史の勉強に使った教材
私が日本史の勉強で使ったのは3つの教材です。
- 山川出版社 日本史図録 第7版
- 山川一問一答日本史アプリ
- ハローアカデミー Flashcards Deluxe 日本歴史に出る写真
この図録と全く同じでなくても良いのですが、図録を見ると分かりやすいです。 4択問題はハローアカデミーでも無料で提供されていらっしゃいます。
その時代の大枠の出来事を理解しよう
まずは、時代ごとに何があったのか大きな出来事を見ていきましょう。 年表を見ながら、いくつの時代に分けて勉強していくのかを考えます。
そして、自分の計画表にその時代を書きこみます。 ※計画通りにいかない事もあるので、余裕を持って振り分けると良いでしょう 復習と書いてあるのは予備日です。

大体1つの時代を3~4日掛けて勉強していくのが望ましいでしょう。1日は大枠の出来事を理解するために、日本史図録のその時代のページを 読みます。最初は太文字の部分を読んで、余裕があれば細かい文字を読んでいきます。 どんな事柄がその時代にあったか、大まかに理解できるようにしましょう。
理解が出来ているか4択問題で繰り返し復習しよう
さて、情報をある程度得たあとは、次はどのくらい理解して覚えたか テストしていきます。これには4択問題を使うのが一番良いでしょう。
私は山川のアプリを使用しましたが、結構細かい問題が出ます。必ず結果を書きとめて、次回はその点数を越えることが出来るように 頑張ってみましょう。
フラッシュカードで絵を見て答える練習をしよう
歴史の流れは、ほぼ4択問題でカバーされるのですが、芸術作品や建造物はさらにフラッシュカードで覚えているか 確認しておくと安心です。
特に、通訳案内士試験では芸術作品や建造物の写真が使用されます 見なくても解ける問題もありますが、重要なものを押さえておけば 1点でも多く点を稼ぐことが出来るので時間に余裕があれば行っておきましょう。
まとめ:通訳案内士の日本史テストを2カ月で合格する為に

これはあくまでも私の勉強法なので、合う合わないはあるかと思いますが、 試験まで残り2カ月で勉強を始めるのに全くどうしていいか分からない、という方は 参考にしていただければ幸いです。
確かに、ここ数年の日本史テストは非常に難しくなりました。
だからこそ、取れる問題を必ず落とさないようにすることが大事だと思います。
歴史は面白いと思いだしたら、どんどん深く勉強したくなる科目です。 また、通訳ガイドになった後も、その知識は絶対に無駄になりません。あと、2カ月!楽しみながら勉強しましょう!!
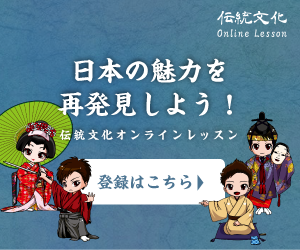
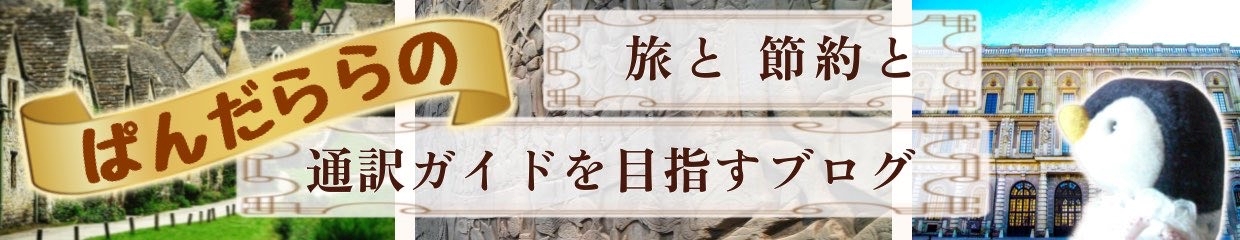




コメント